「優柔不断で、決断力がない」
「いつも誰かに決めてもらっている」
そんな人は、自分で決めるトレーニングを始めましょう。
小さな決断を繰り返す
先日、むすめとプチ旅行をしました。
神奈川県にホテルをとり、いくつか用事を済ませたんですね。
何時に出発して、どのようにして用事を済ませ、食事はどこで何を食べるのか。
そういったことを全部、自分で決める必要がありました。
(人によっては、「そんなの当たり前」という人もいるかもしれませんね)
全部、自分で決めるとなると、自分の頭でしっかり考える必要があります。
ときに瞬時に判断をしなくてはいけないことも。
たとえば、かぎられた時間内に食事をとらなくてはいけないとき。
「どうしよう……」と悩んでいるヒマはありません。
パッパと決めていかなければいけないので、おのずと決断力が育つんです。
重要な決断をしなければいけないとき、日頃の小さな決断の経験が役に立ちます。
いつも自分で決めていれば、自然と大きな決断もできるようになります。
決断力を育てるために、日頃から、自分で選ぶ経験をしてみてはいかがでしょうか。
そのために、ひとりで過ごす時間を作ったり、旅行の際に、率先して計画を立ててみるのがオススメです。
軌道修正できることが大事
「一度決めたら、変えてはいけない」
もし、こう思っているなら、決断することに恐怖を感じるのも当然かもしれません。
まちがえても修正できないとなると、決断に慎重になるのもうなずけます。
軌道修正できないと思ったら、決断が怖くなってしまいます。
でも、本当は、軌道修正していいんです。
一度決めたことでも、変更してOK。
試しに決めたことを実践してみて、「違うな」と思ったら、別の道を選択すればいい。
そのときは、しっかり頭で考えること。
なんとなくで動いてしまうと、決断力が育ちません。
なぜその決断をするのか、自分の決断の基準を明確にすることが大切です。
そうすれば、そこで身につけた決断力は、次の決断のときにも役立つんです。
「決断力を育てる」という視点
かつての自分は、決断力について、「あるか、ないか」の二択で考えていました。
そのため、優柔不断になることが多かったわたしは、「決断力がない」ということになってしまっていたんです。
でも、本当は、決断力にもレベルがあり、
・ほとんど自分で決められない
・小さな決断ならできる
・大きな決断もできる
といったように、グラデーションがあると思うんですね。
わたしは、「決断力を育てる」という視点が大事なのだと思っています。
今の決断力が20ならば、それを25に変える努力をする。
それができたら、30に……という感じで、少しずつレベルアップしていくんです。
「あるか、ないか」では判断基準が二択になってしまいます。
そうではなく、もっと細かな目で見て、
「前よりも、少し決断力がついた」
と、自分を評価できるようになる必要があると思います。
おそらく、あなたも、自分の決断力を0から100までで数値化するなら、「0」ではないのでは?
決断力は育てるもの。
「あるか、ないか」ではないんです。
これから、決断力のレベルを1つずつ上げていきましょう。
そのために、ひとりでお出かけしてみるのもオススメです。
自分らしい人生のために決断力は不可欠です。
ぜひ今日は、いつも人に委ねてしまっていることを、自分で決めてみてください。
そのうちに、大きな決断ができるようになります。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
【複雑性PTSD】「親といるときの自分」と違う、「新しい自分」の割合を増やす
【複雑性PTSD】自分の子どもに、わたしと同じようなつらさを味わってほしくない。育児のルールに苦しむママへ
【複雑性PTSD】愛情あふれる家庭で育った夫と条件つきの愛情で育ったわたしの現在
【複雑性PTSD】生きづらさにつながる、親子の感覚のズレ。自分の感受性に合った環境を選び直すこと
decisiveness
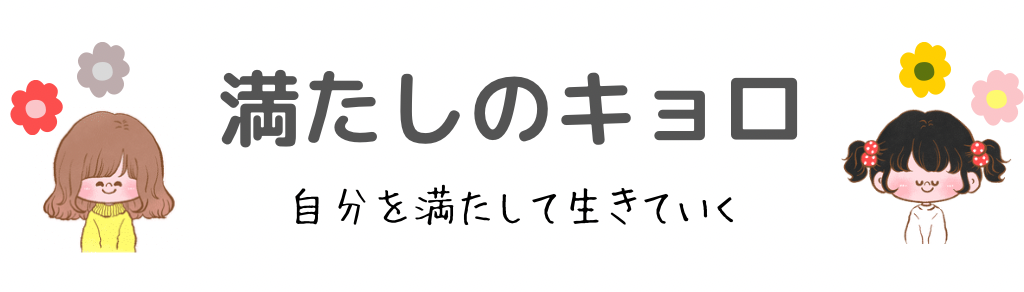









コメントを残す